私たちの身近にある有名な山や建物の高さを、みなさんは覚えていますか?
日本を代表する富士山、世界一高い山エベレスト、そして東京を象徴する建物である東京タワーとスカイツリー。
それぞれの高さには、覚えやすくするためのユニークなコツがあります。
この記事では、数字をただ暗記するだけではなく、語呂合わせやイメージを使って、楽しく覚える方法を紹介していきます。
知っていると話のネタになるだけでなく、学校の授業やクイズ、旅行のときにも役に立つかもしれません。
富士山の高さをスムーズに覚えるための語呂合わせ
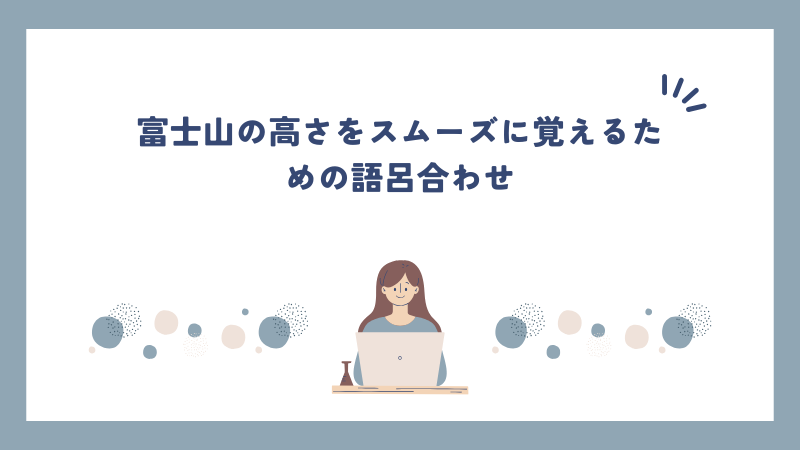
日本で最も高い山、富士山の標高は「3776メートル」です。
この数字はシンプルに見えて、いざ聞かれるとすぐには出てこない人も多いかもしれません。
そこで登場するのが語呂合わせのテクニックです。
たとえば、「3776(みな、なむ)」という読み方にして、「みんなで南無阿弥陀仏」と唱える場面を想像してみましょう。
富士山は昔から神聖な山として、人々に大切にされてきました。
そのため、朝に手を合わせて「南無阿弥陀仏」と祈るイメージは、自然に心に残りやすいです。
このように、数字とイメージをつなげることで、記憶にしっかりと定着させることができます。
もっと正確に覚えたい人には、「3776.24メートル」という細かい数値もおすすめです。
このときは、「みな、なむ、にし」と覚えると良いでしょう。
「にし」は「西」と結びつけて、みんなが西の方角に向かって静かに手を合わせる風景を思い浮かべてみてください。
心の中に情景が描ければ、それだけで忘れにくくなります。
高さをイメージで楽しく覚える!エベレスト・東京タワー・スカイツリー
ただ数字を並べるよりも、そこに面白いイメージや言葉の響きをつけると、記憶にぐっと残りやすくなります。
ここでは、エベレスト、東京タワー、スカイツリーという3つのシンボルを取り上げ、それぞれの高さを楽しく覚える語呂合わせをご紹介します。
高さの記憶術まとめ
| 名称 | 高さ | 語呂合わせ | イメージの例 |
|---|---|---|---|
| エベレスト | 8848m | ははのしわ | 地球のお母さんが、しわをよせて世界一の山を作り出した |
| 東京タワー | 333m | みみみっ | 「みみみっ」と電波が飛び交う、元気いっぱいの電波塔のイメージ |
| 東京スカイツリー | 634m | むさし | 剣豪・武蔵がそびえる巨大なツリーに立ち向かう迫力あるシーン |
エベレストは「ははのしわ」という語呂合わせを使い、大きな山を地球という母が作ったという物語にすると覚えやすくなります。
東京タワーは「333(みみみっ)」と読むことで、アンテナが活発に動いている様子を連想できます。
スカイツリーの「634」は、「むさし」と読めるので、宮本武蔵が空に向かって伸びる巨大なタワーを見上げている情景を思い描いてください。
世界の山々と比べると?富士山の世界ランキング
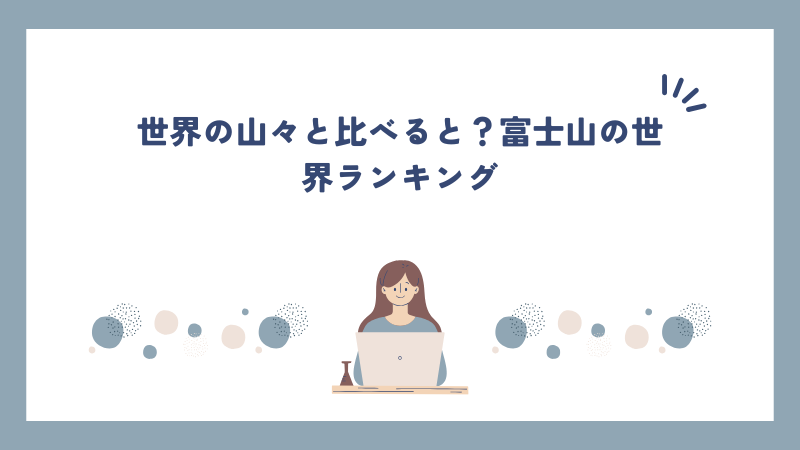
日本で一番高い富士山ですが、世界の山々の中ではどのくらいの位置にあるのでしょうか?
実は、富士山より高い山はたくさん存在しています。
その中でも特に高い山が集まっているのが、ヒマラヤ山脈やカラコルム山脈という地域です。
以下の表を見てみましょう。
世界の高い山トップ10
| 順位 | 山の名前 | 標高 | 山脈 |
|---|---|---|---|
| 1位 | エベレスト | 8848m | ヒマラヤ山脈 |
| 2位 | K2 | 8611m | カラコルム山脈 |
| 3位 | カンチェンジュンガ | 8586m | ヒマラヤ山脈 |
| 4位 | ローツェ | 8516m | ヒマラヤ山脈 |
| 5位 | マカルー | 8463m | ヒマラヤ山脈 |
| 6位 | チョー・オユー | 8201m | ヒマラヤ山脈 |
| 7位 | ダウラギリ | 8167m | ヒマラヤ山脈 |
| 8位 | マナスル | 8163m | ヒマラヤ山脈 |
| 9位 | ナンガ・パルバット | 8126m | ヒマラヤ山脈 |
| 10位 | アンナプルナ | 8091m | ヒマラヤ山脈 |
このように、標高8000メートルを超える山は、世界に14座も存在しています。
また、7000メートル級の山も88座、6000メートル以上の山も72座あり、富士山よりも高い山は世界に509以上あるのです。
日本では特別な存在である富士山も、世界スケールで見ると中くらいの高さと言えるでしょう。
昔はもっと高かった?富士山の高さの変化
現在の富士山は「3776メートル」とされていますが、昔は少し高かったという記録があります。
1885年の古い測量では、「3778メートル」とされていたのです。
この2メートルの差は、測量の技術が未発達だったからではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、1817年に伊能忠敬が作成した日本地図は、現代の地図と比べてもほとんど誤差がないほど正確でした。
つまり、当時の日本にはすでに高い測量技術があったのです。
では、なぜ今より高かったのでしょうか?
それは、1923年に発生した関東大震災による地殻変動が関係していると言われています。
この大きな地震の影響で地盤が沈み、その結果、富士山の標高が2メートルほど下がったのではないかと考えられています。
1926年に行われた新しい測量では、「3776メートル」と記録され、現在までその数値が使われています。
富士山の高さはどうやって測ってるの?
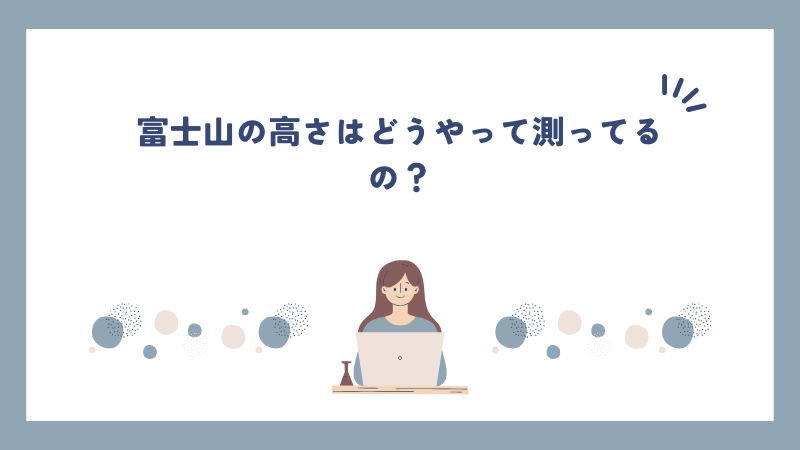
富士山のような大きな山をどうやって測るのか、ちょっと気になりますよね。
実は、個人の身長を測るようにメジャーで測るわけではありません。
山の高さを測るときは、まず「基準となる高さ」が必要です。
日本では「日本水準原点」という場所があり、ここが高さの出発点になります。
この水準原点は、東京にあり、安定した場所に設置されています。
なぜなら、海の高さは潮の満ち引きで変わってしまうからです。
この基準点から、山のふもとにある三角点までを測り、そこから富士山の頂上までの高さを計算で出します。
三角点は、地図にも使われる大事な場所で、正確な位置がわかるように設置されています。
こうして、いくつかの角度や距離を測ることで、山の高さが正確に求められているのです。
まとめ
富士山、エベレスト、東京タワー、そして東京スカイツリー。
これらの高さを知っているだけで、ちょっとした知識として話のタネになります。
語呂合わせやイメージを使えば、難しい数字も楽しく覚えられます。
今回紹介した方法をぜひ活用して、家族や友達にも教えてあげてください。
いつか役立つ場面がきっと訪れるはずです。


